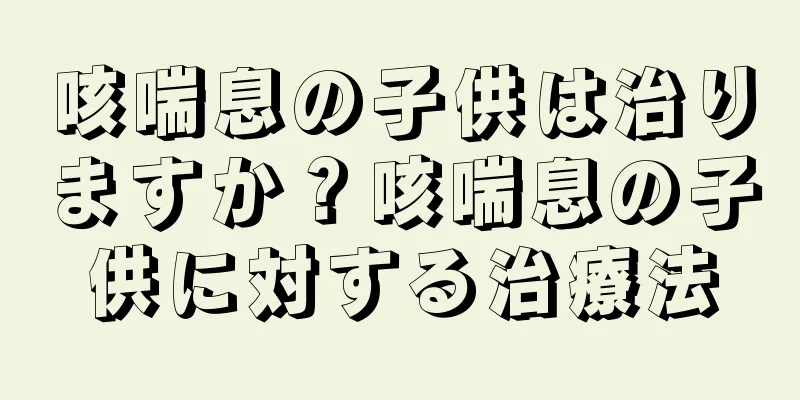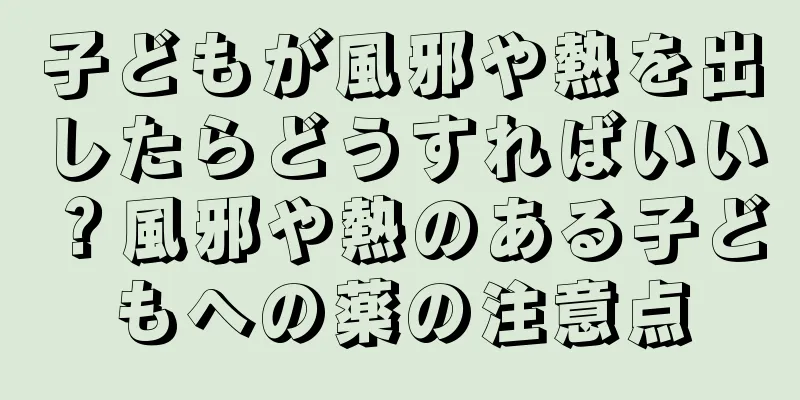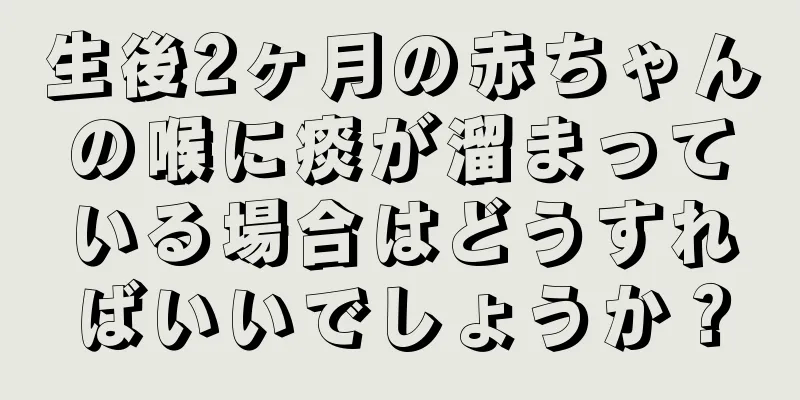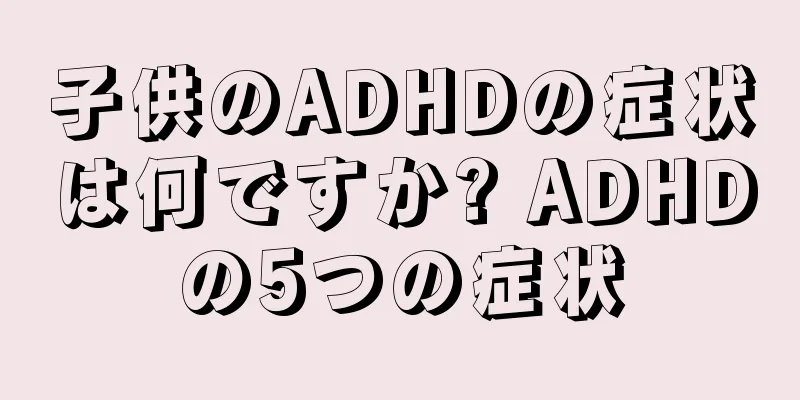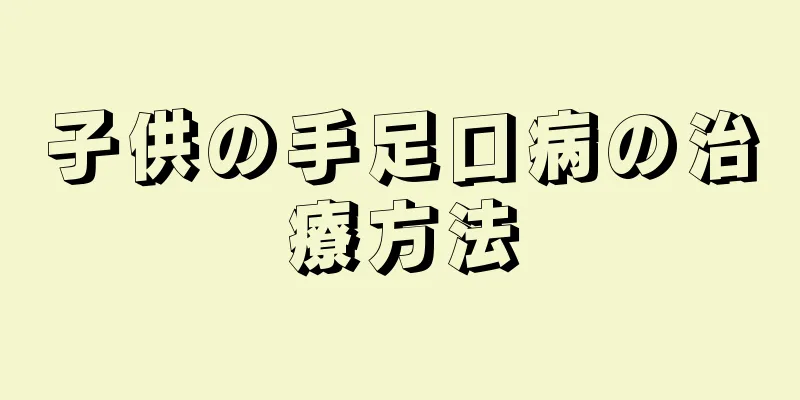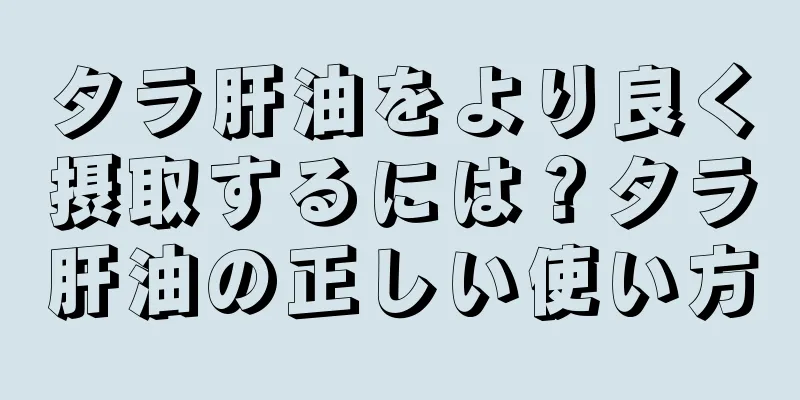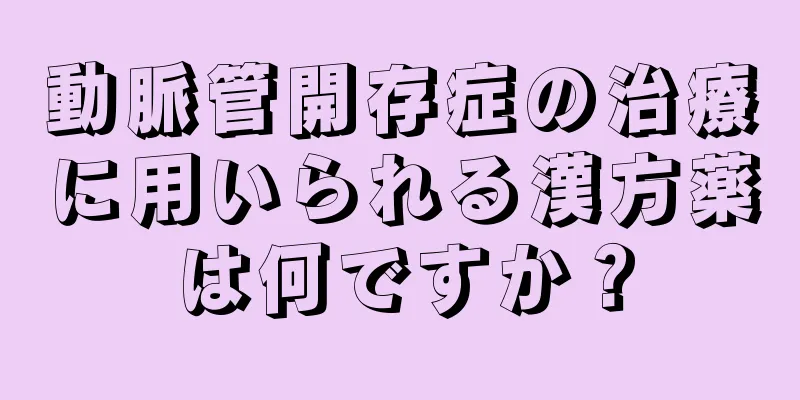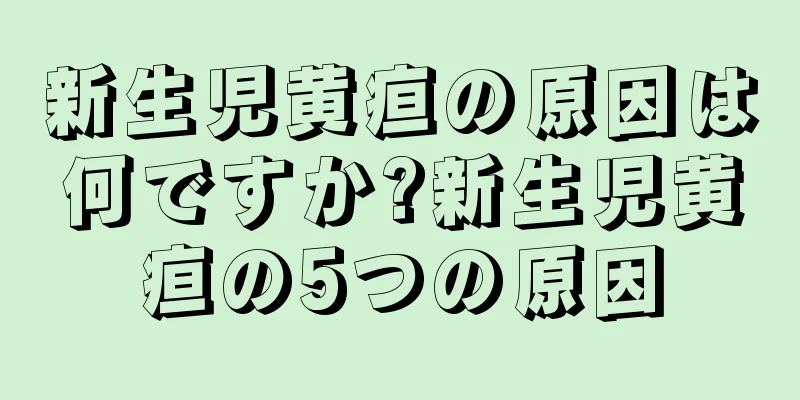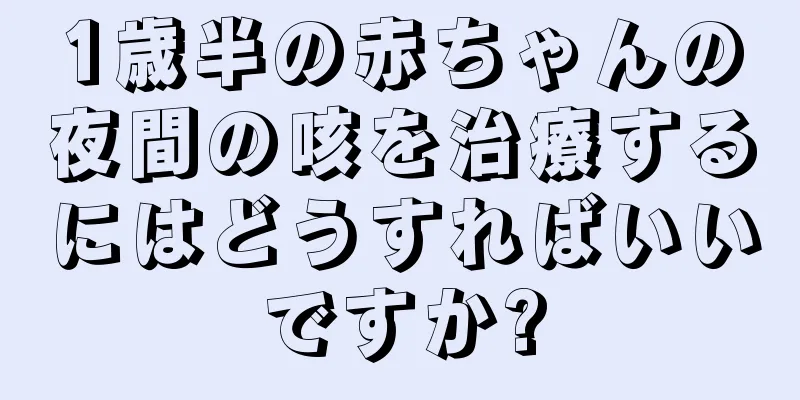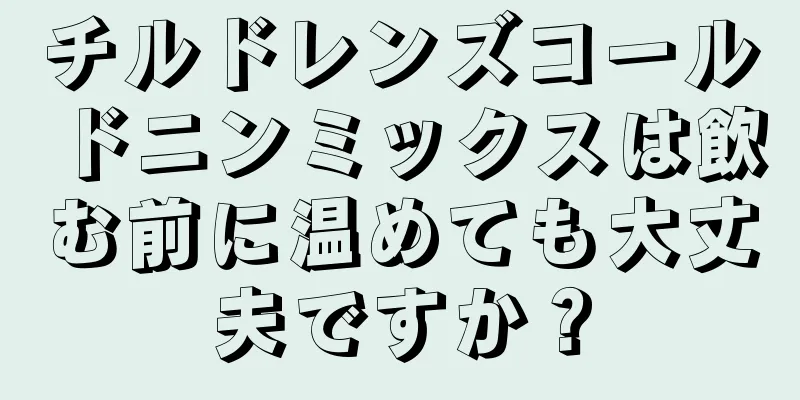先天性黄疸の原因は何ですか?
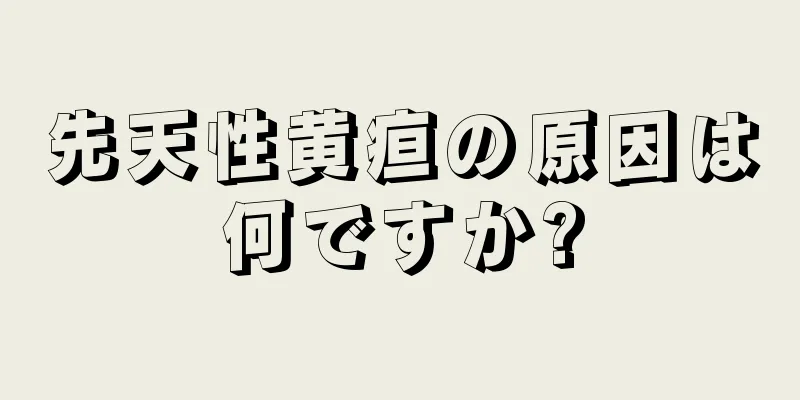
|
先天性黄疸は、母乳育児、ビタミン E 欠乏、先天性代謝異常、胆汁排泄異常、薬物要因に関連している可能性があります。早めに治療を受けることが推奨されており、医師の指導のもと、対象を絞った一般治療、理学療法、薬物治療を行うことができます。詳細は以下の通りです。 1. 授乳:母乳中のグルクロニダーゼのレベルが高すぎるため、腸内でグルクロン酸とビリルビンが分離し、腸内の非抱合型ビリルビンの含有量が増加し、黄疸を引き起こします。新生児の誕生後できるだけ早く母乳育児を開始し、十分な母乳摂取を確保する必要があります。未熟児や低出生体重児などの高リスク要因を持つ新生児の場合、黄疸の早期発見と治療を促進するために、ビリルビン値を定期的に監視する必要があります。 2. ビタミン E 欠乏症: ビタミン E が欠乏すると、細胞膜が酸素フリーラジカルによる攻撃を受けやすくなり、細胞膜の損傷や赤血球の破裂を引き起こします。赤血球が破裂した後に放出されるビリルビンは体内で正常に代謝されず、血液中のビリルビン濃度が上昇し、黄疸を引き起こします。ナッツや植物油など、ビタミン E が豊富な食品をもっと食べましょう。症状が重い場合は、医師のアドバイスに従って、銀枝黄内服液、銀辰五菱丸、ウルソデオキシコール酸カプセルなどの薬剤を使用して治療することができます。 3. 先天性代謝異常:肝臓内の特定の酵素が欠乏し、ビリルビンの代謝が妨げられ、体内のビリルビン濃度が上昇し、黄疸を引き起こす可能性があります。症状が重篤ではなく、明らかな不快症状がない患者の場合、お粥などの軽くて消化しやすい食べ物を食べ、十分に日光を浴びることで症状を緩和することができます。症状が重い場合は、青色光を使用して非抱合型ビリルビンを光酸化し、水溶性ビリルビンに変換し、尿や胆汁を通じて排泄することで治療効果を得ることができます。 4. 胆汁排泄異常:胆管閉塞が起こると胆汁が排泄できず、胆汁とともにビリルビンも体外に排泄されないため、血中のビリルビン濃度が上昇し、黄疸を引き起こします。妊婦は感染症の発生を防ぐために、頻繁に手を洗ったり入浴したりするなど、良好な個人衛生習慣を維持する必要があります。症状が重い場合は、医師のアドバイスに従って、抗炎症・利尿薬、ウルソデオキシコール酸カプセル、プレドニゾン酢酸塩錠などの薬剤を使用して治療することができます。 5. 薬剤要因: 特定の薬剤はビリルビンの代謝を妨げ、血液中のビリルビン濃度の上昇を引き起こし、黄疸を引き起こす可能性があります。関連する薬剤は直ちに中止する必要があります。薬を中止しても黄疸が治まらない場合は、医師の指導のもと、グリチルリチン酸配合錠、ビシクロル錠、肝臓保護錠などの薬剤を使用することができます。 上記の理由に加えて、赤血球酵素の欠陥によっても引き起こされる可能性があります。適度に日光を浴びると黄疸の緩和に役立ちますが、日差しが強いときは日光を浴びないようにしてください。 |
<<: 成人の場合、手術を行う前に動脈管開存症を何 mm 閉じておく必要がありますか?
推薦する
子供の咳や喘息は治りますか?子供の咳の症状は何ですか?
子供の咳や喘息は治せます。病気を遅らせず、できるだけ早く病院に行って検査と治療を受けることをお勧めし...
黄疸性肝炎は治癒できますか?黄疸性肝炎をより良く治療するにはどうすればいいですか?
黄疸性肝炎は比較的一般的な肝臓疾患で、通常は子供に発生します。親は子供を適時に検査し、治療することを...
赤ちゃんの下痢を予防するには?子供の下痢の原因は何ですか?
小児下痢症は、主に下痢と複数の病原体や要因によって引き起こされる一群の疾患です。主な特徴は排便回数の...
小児下痢の鑑別
夏の到来とともに、さまざまな冷たい食べ物が登場しますが、子どもたちにとっては、おいしい食べ物がまたひ...
おたふく風邪にかかった子供は咳をしますか?
子どもはおたふく風邪にかかったときに咳をすることがありますが、すべての咳がおたふく風邪に関連している...
赤ちゃんの黄疸が強い場合の症状は何ですか?
乳児の黄疸が高度になると、皮膚や白目の黄色化、眠気、食欲不振などの症状が現れることがあります。重症の...
子供の肺炎を予防する方法
子供の肺炎を予防するにはどうすればいいでしょうか?肺炎は子供によく見られる難治性の病気です。完全に治...
赤ちゃんの鉄欠乏症の症状は何ですか?赤ちゃんが鉄欠乏症になったときに注意すべきことは何ですか?
赤ちゃんの鉄欠乏症の症状は、イライラ、活動性の低下、顔色が悪い、食欲不振、吐き気、めまいなど、多岐に...
夜間の子供の咳の治療法 夜間の子供の咳の治療法
赤ちゃんが夜間に咳をする場合は、室温を調整し、分泌物を排出するために背中を軽くたたき、喉を潤すために...
生理的黄疸のある新生児は眠気を引き起こしますか?新生児の生理的黄疸の具体的な症状を知る
新生児生理的黄疸は新生児によく見られる症状です。通常、生後2~3日で皮膚が淡黄色に変わります。食欲不...
おたふく風邪の最も一般的な治療法
ご存知のとおり、おたふく風邪は感染症です。患者は発熱や顔面の腫れなどの臨床症状を示すことが多いです。...
新生児の黄疸を軽減する方法と服用すべき薬
新生児黄疸は医師の指導のもと治療する必要があります。一般的に使用される薬剤には銀枝黄内服液、フェノバ...
子供の湿疹は発熱を引き起こすことがありますか?一般的にはそうではない
小児湿疹は一般的に発熱症状を引き起こしませんが、症状が重篤な場合は二次感染を引き起こし、発熱を引き起...
手足口病の最良の治療法
手足口病は、コクサッキーウイルスA群16型やエンテロウイルス71型などのエンテロウイルスの感染によっ...
子どものインフルエンザと風邪の見分け方 子どものインフルエンザと風邪の見分け方
1. 風邪やインフルエンザはウイルスによって引き起こされるウイルス性の風邪です。 2. インフルエン...