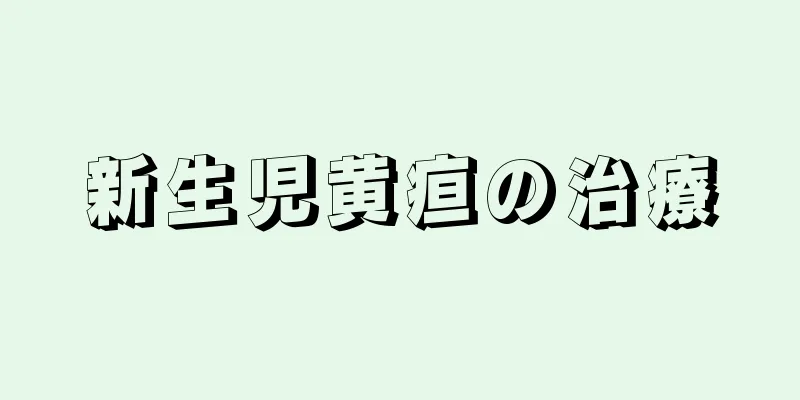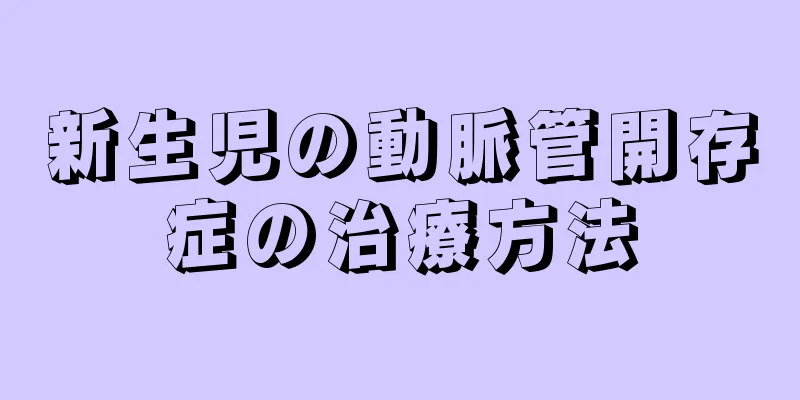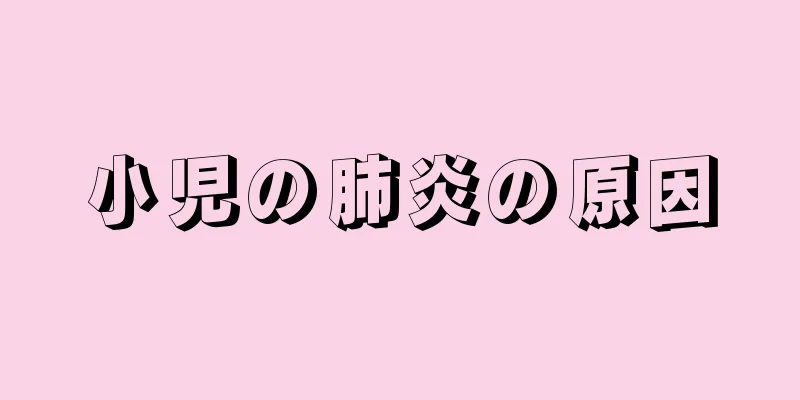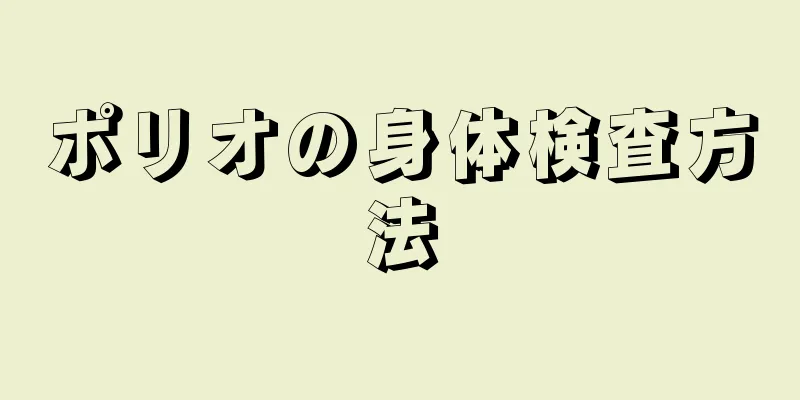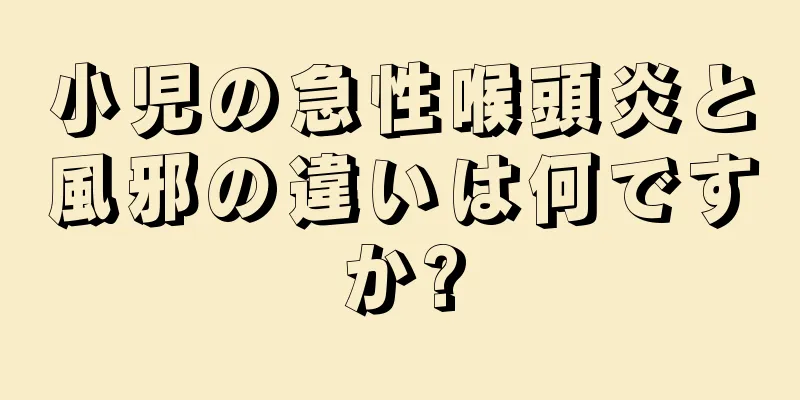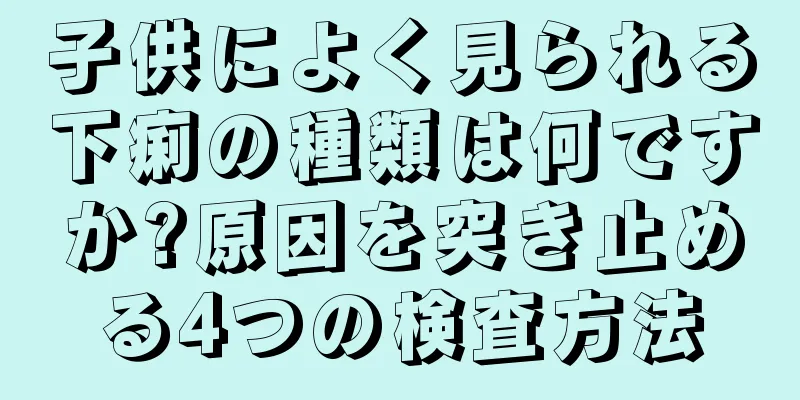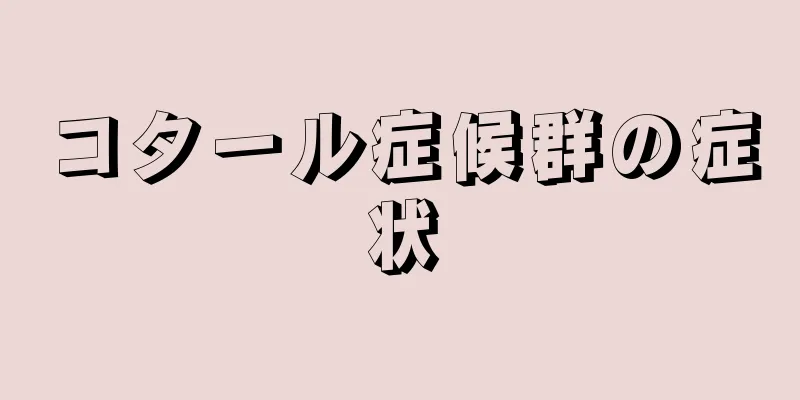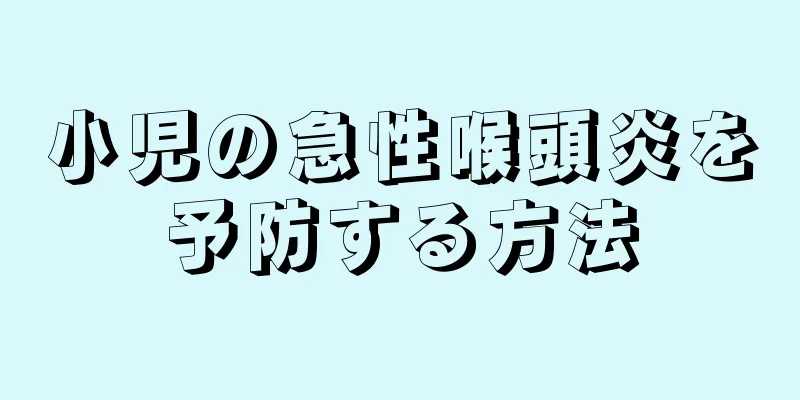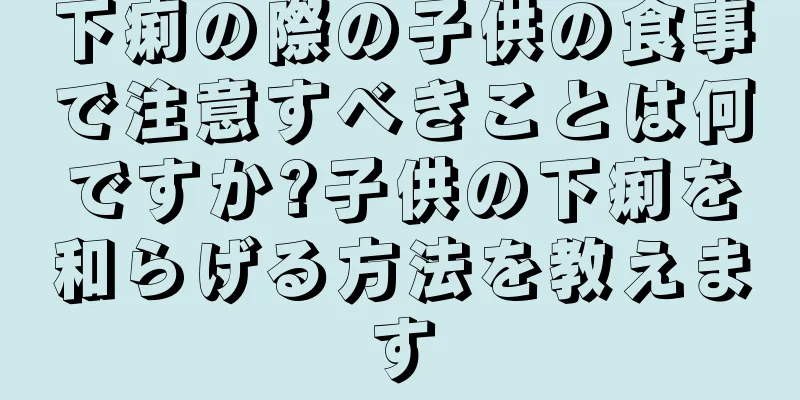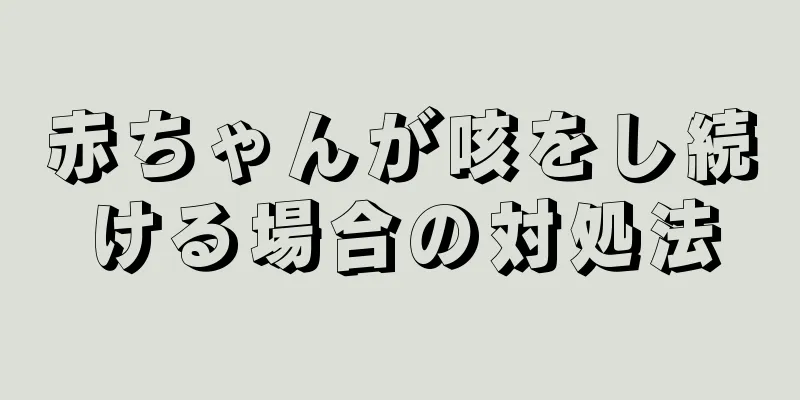動脈管開存症に対する手術アプローチの選択
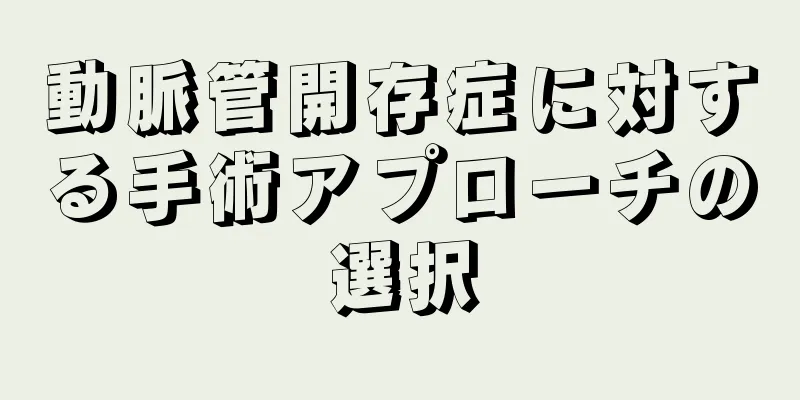
|
動脈管開存症の手術選択肢は何ですか?動脈管開存症には多くの合併症があります。動脈管開存症についての知識を学ぶと同時に、動脈管開存症の合併症の発生を予防することにも注意を払う必要があります。この病気が発生した場合、どのような手術法を選択すべきでしょうか? (I)動脈管結紮術は、動脈管が細く、動脈管壁が柔らかく弾力性があり、細菌感染を起こしていない幼児に適している。 1.切開:左後外側開胸。第4肋間または第5肋間から胸部に入ります。 2.左下葉を前方下方に引っ張って、左肺動脈、横隔膜神経、迷走神経によって形成される管状三角形を露出させます。この領域では継続的な震えが触知できる場合があります 3.横隔膜胸膜を横隔膜神経と迷走神経の間で縦方向に切断すると、大動脈と肺動脈の間の管を露出させることができます。 4.ブロッキングバンドは、自由カテーテルの上端と下端の大動脈に配置されます。 5.カテーテルの前端と上下端を慎重に分離し、その後、カテーテルの後壁を鈍的に分離します。手術中に左反回神経を傷つけないようにしてください。結紮のために十分なカテーテルの長さを確保してください。 6.動脈カテーテルを指で押すか、カテーテルクランプで約 10 分間締め付けて閉塞テストを実行します。血圧の低下、心拍数の増加、不整脈、肺動脈圧の上昇が見られる場合は、カテーテルを閉じないでください。そうでなければ、手術は続行できます。 7.小さな直角鉗子のガイドの下で、2 本の No. 10 絹糸をカテーテルの後壁に通しました。麻酔科医は血圧を8N10kPaまで下げた後、まずカテーテルの大動脈端を結紮しました。結紮糸は肺動脈端の震えが消えるまで徐々にゆっくりと締め付け、その後少し締め付けてから肺動脈側を結紮します。 2 本の糸の間に別のステッチを挿入することもできます。 8.縦隔胸膜を縫合します。閉鎖式胸腔ドレーンを設置します。痰を吸引し肺を拡張します。胸壁の切開部を縫合した。 (ii)動脈管の切断と縫合は、年長児、動脈管が太くて短い、シャント量が多い、または動脈管に感染がある小児に適しています。 1.切開:左後外側開胸。第4肋間または第5肋間から胸部に入ります。 2.左下葉を前方下方に引っ張ると、左肺動脈、横隔膜神経、迷走神経によって形成される管、すなわち隅角領域が露出します。この領域では継続的な震えが触知できる場合があります 3.横隔膜胸膜を横隔膜神経と迷走神経の間で縦方向に切断すると、大動脈と肺動脈の間の管を露出させることができます。 4.ブロッキングバンドは、自由カテーテルの上端と下端の大動脈に配置されます。 5.カテーテルの前端と上下端を慎重に分離し、その後、カテーテルの後壁を鈍的に分離します。操作中は、左反回神経を傷つけないようにします。 6.大動脈側にポッツスミスクランプを設置し、肺動脈側に動脈クランプを2つ設置しました。 7.カテーテルを切断しながら大動脈側を前後に連続的に縫合します。 8.肺動脈側も同様に縫合しました。 |
推薦する
おたふく風邪の看護対策
最近では、おたふく風邪に悩まされている人がかなりいます。この病気は、実は治療がそれほど難しくありませ...
小児の急性喉頭炎の早期治療の費用は高いですか?
現在、小児の急性喉頭炎の発症率は上昇しており、患者に大きな損害をもたらしています。原因は比較的複雑で...
川崎病を治すにはどのくらい時間がかかりますか?
川崎病は治るのにどれくらいの時間がかかりますか?川崎病といえば、誰もが知らない病気です。実は川崎病の...
体質性黄疸の治療方法
一般的に言えば、体質性黄疸はより重篤な慢性黄疸であり、患者の先天的な肝細胞によるビリルビンの取り込み...
新生児黄疸は知能に影響しますか?新生児黄疸の4つの主な危険に注意
新生児黄疸には、生理的黄疸と病的黄疸など、さまざまな種類があります。生理的な黄疸は時間が経つと治りま...
子供の慢性咳嗽の症状は何ですか?
小児の慢性咳嗽は、上気道咳嗽症候群、咳嗽変異型喘息、胃食道逆流性咳嗽などに分けられます。咳嗽の症状は...
子供のヘルニアを治療する最適な時期
小児ヘルニアを治療するのに最適な時期は通常、子供が約 1 歳のときです。この期間の手術効果はより良く...
急性喉頭炎の子供はバナナを食べても大丈夫ですか?
急性喉頭炎の子供は適度にバナナを食べることができますが、バナナが氷や冷たいものでないことを確かめ、低...
筋ジストロフィーを効果的に治療するにはどうすればよいでしょうか? 伝統的な中国医学は筋ジストロフィーの治療に大きな効果があります。
筋ジストロフィーは発症以来、その治療に画期的な解決策がなかったため、筋ジストロフィーの治療法の導入に...
1歳児の咳の治療法 1歳児の咳の治療法
天候が乾燥しすぎて子供が水分をあまり摂取しなくなると、咳の症状が出る可能性が高くなります。急に気温が...
おたふく風邪とは何ですか?
おたふく風邪とは何でしょうか?おたふく風邪は急性の感染性呼吸器疾患です。若い頃におたふく風邪にかかっ...
赤ちゃんが咳や鼻水、下痢をしている場合はどうすればいいですか? 赤ちゃんが咳や鼻水、下痢をしている場合は、どのように薬を使えばいいですか?
赤ちゃんは抵抗力が非常に弱いため、咳、鼻水、下痢は重篤な症状です。一般的には細菌やウイルスの感染によ...
小児の先天性心疾患の予防と治療方法
多くの若いカップル、特にこの病気の家族歴があるカップルは、先天性心疾患について聞くと非常に恐怖を感じ...
ポリオは大人にも感染しますか?
ポリオは主に接触によって感染しますが、成人も感染する可能性があります。予防策としては、ワクチン接種、...
黄疸の症状は何ですか?
黄疸とは、ビリルビン代謝障害により血清中のビリルビン濃度が上昇し、強膜、皮膚、粘膜などの組織や体液が...