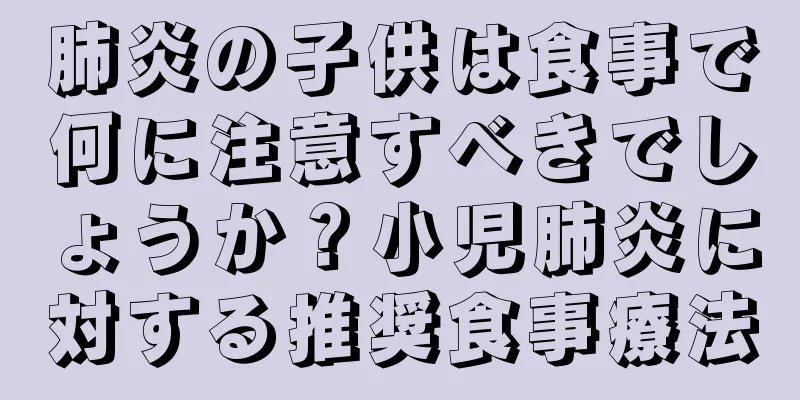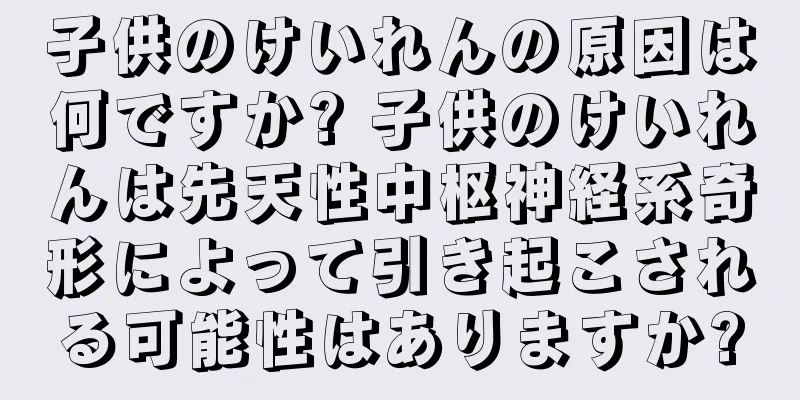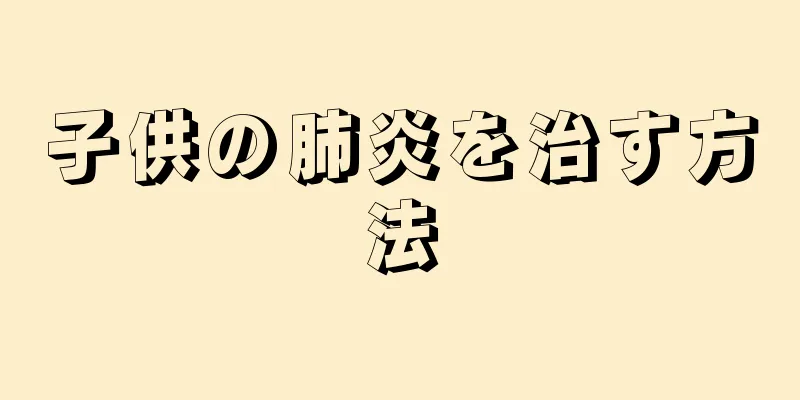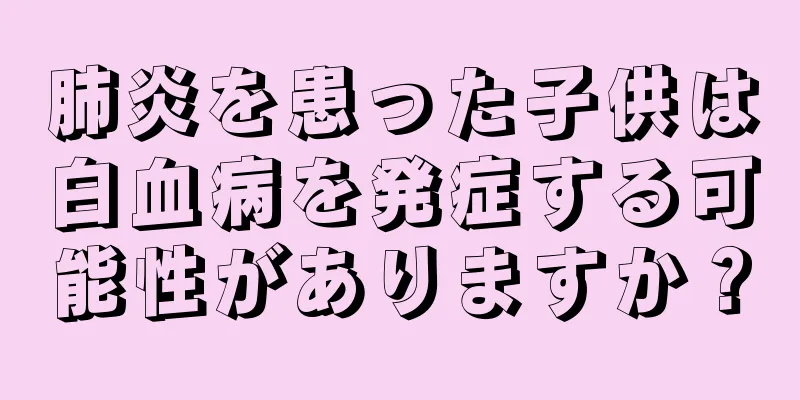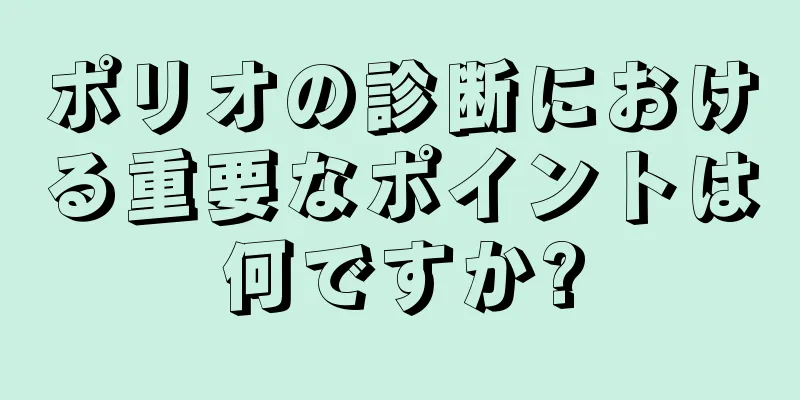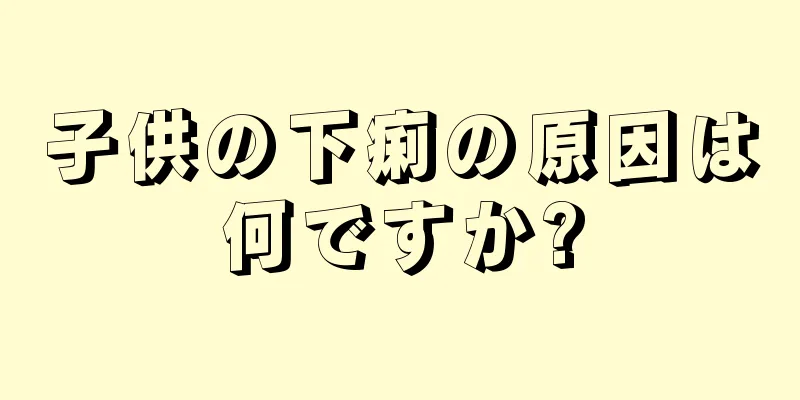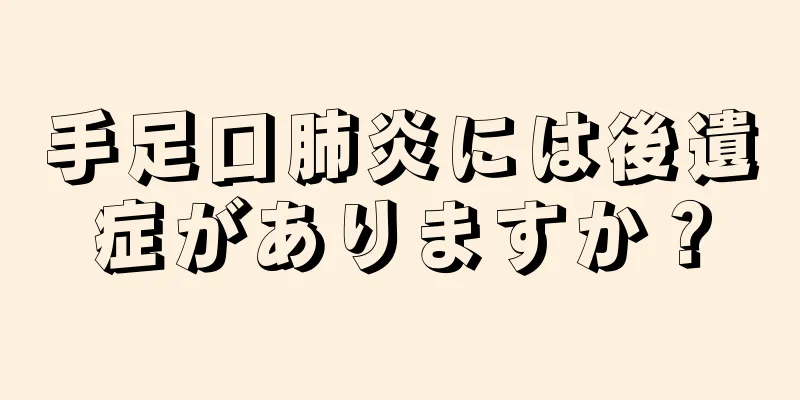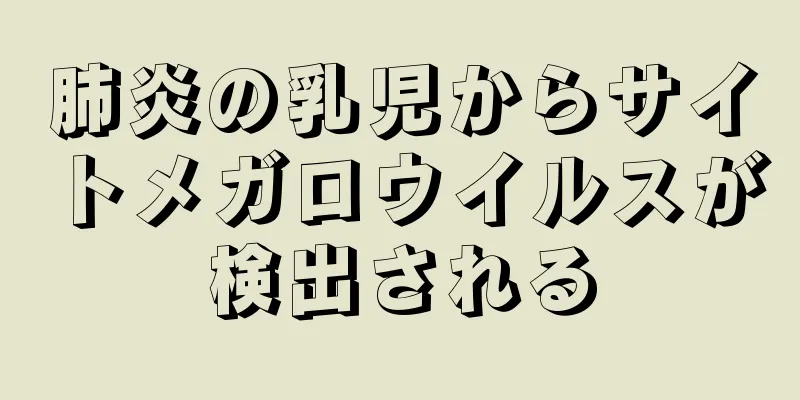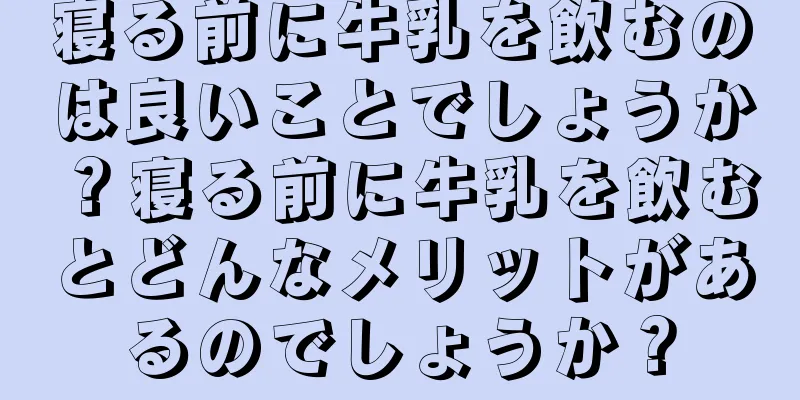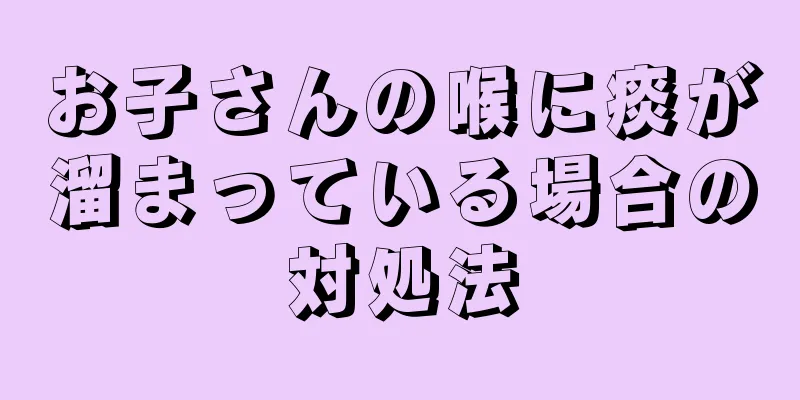新生児黄疸を治す方法は何ですか?
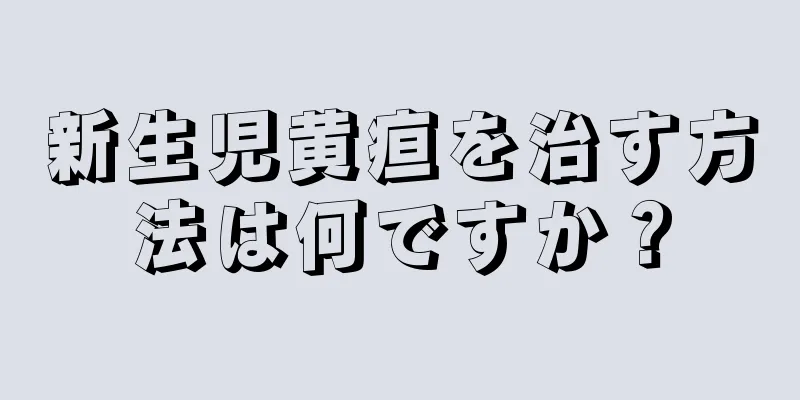
|
新生児黄疸は新生児期によく見られる病気で、ほとんどの赤ちゃんが出生後に黄疸を発症します。一般的に言えば、親は過度に心配する必要はなく、黄疸の異常な変化を適時に観察する必要があります。小児黄疸のほとんどは正常な黄疸であり、異常な黄疸を示す新生児はごくわずかです。では、新生児黄疸を治す方法にはどのようなものがあるのでしょうか?見てみましょう。 1. 光療法 新生児を裸のまま紫外線の下に置きます。片面のみに光を照射するか、両面同時に光を照射するかを選択できます。治療中は、網膜の損傷を防ぐために目を保護し、性器と肛門をおむつで覆う必要があります。紫外線の作用により、体内の過剰なビリルビンは特定の水溶性物質に変換され、尿中に排出されます。この方法により、新生児のビリルビン濃度を 7 mg/L まで下げることができます。あるいは、新生児を毛布状の黄疸治療装置で包み、光線療法を行うことで、同様の効果が得られます。 予防 (1)この治療法は、通常4日間以上連続して行うべきではない。患者が4日以内に回復しない場合は、輸血療法を考慮する必要がある。 (2)主な副作用は発疹と下痢ですが、治療後は正常に戻ります。 2. 血液交換療法 これは重度の溶血性黄疸を患っている小児に対する応急処置です。この治療法の仕組み: (1)体内の免疫抗体を除去することができる。 (2)血液中のビリルビン濃度を低下させる (3)溶血によって引き起こされる貧血や酸素不足などの一連の副作用を改善する。 3. ビリルビン再吸収防止法 新生児に母乳を与えると、消化管内に独自のプロバイオティクス菌叢を構築するのに役立ちます。これらの有益な細菌はビリルビンを分解し、糞便を通して体外に排出することができます。あるいは、新生児に活性炭を経口投与してビリルビンの再吸収を防ぐという方法もありますが、この方法は光線療法と組み合わせて使用する必要があります。 4. 酵素誘導療法 フェノバルビタールなどの典型的な酵素誘導剤は、肝細胞の機能を刺激し、ビリルビンを遊離状態から結合状態に変換することができます。クロラミンと併用すると、治療効果が高まります。注意:黄疸が長期間続き、症状が重篤な場合は、病的黄疸の可能性を考慮し、赤ちゃんは光線療法を受け、さらに身体検査を受ける必要があります。 5. アルブミン アルブミンは血液中の遊離ビリルビンを吸収し、それが脳細胞に結合するのを防ぎます。この療法は核黄疸の治療に効果的です。 6. 副腎皮質ホルモン このタイプの製品は抗原と抗体の結合を妨げ、それによって溶血を軽減します。同時に、肝臓のグルクロン酸トランスフェラーゼの活性を高め、ビリルビンのグルクロン酸抱合を促進します。プレドニゾンは経口摂取することができ、ヒドロコルチゾンは静脈内投与することができます。多くの副作用があるため、症状が改善したら投与量を減らすか中止する必要があります。光線療法との併用は推奨されません。この種の薬剤には抗免疫作用があるため、感染者は注意して使用する必要があります。 7. 伝統的な中国医学 小黄里顆粒、三黄煎じ液などの医薬品。 上記で紹介した記事の内容を踏まえて、新生児黄疸の治療方法については皆さんもある程度理解できたと思います。お子さんが黄疸になっても慌てないでください。すぐに医師に相談し、注意深く観察してください。黄疸は通常、一定期間内に自然に消えます。黄疸が治まらない場合は、症状を遅らせずに、早めに医師の診察と治療を受けてください。 |
推薦する
1歳の赤ちゃんがカルシウム不足になったらどうすればいいですか?赤ちゃんにカルシウムを補給するときに注意すべきことは何ですか?
1歳の赤ちゃんが夜寝ているときにいつも突然目覚めたり、泣き止まなかったり、寝た後に大量に汗をかいた...
小児における末期腎疾患の治療
子どもは国の未来です。子どもが健康に成長できるかどうかは、国の将来の発展に関係しています。しかし、子...
手足口病は潜伏期間中に伝染しますか?
子供の手足口病は、潜伏期間中に伝染します。潜伏期間の終わりには、症状がまだ現れていなくても、患者の体...
黄疸が長期にわたって続くと何か害がありますか?
長期にわたる高黄疸は体内の複数の臓器に損傷を引き起こす可能性があるため、介入と治療のためにできるだけ...
子供が肺炎や息切れを起こした場合の対処法
子供が肺炎で息切れを起こした場合はどうすればいいでしょうか?子供が肺炎や息切れを起こした場合、治療し...
下痢を患う小児の脱水症状の程度と性質
子どもが下痢により脱水症状を起こした場合、脱水症状の程度や性質に応じて適切な治療措置を講じる必要があ...
赤ちゃんの黄疸の予防と治療方法
1. 妊婦に肝炎の病歴がある場合、または病的黄疸のある赤ちゃんを出産したことがある場合は、出産前に関...
赤ちゃんが黄疸を発症するまでに何日かかりますか?
「新生児黄疸」とは、新生児期に体内にビリルビンが蓄積し、血液中のビリルビン濃度が上昇し、皮膚、粘膜...
小児の病的黄疸の症状は何ですか?次の4つの症状に注意してください
黄疸については誰もがある程度理解しています。新生児が黄疸の症状を示しても、それが正常な生理的反応だと...
生後 80 日の赤ちゃんが咳をしたらどうすればいいですか? 生後 80 日の赤ちゃんが咳をするのは肺炎のせいでしょうか?
親愛なる保護者の皆様、赤ちゃんは生後 80 日とまだ非常に小さく、勝手に薬を使用することはできないこ...
小児の肺炎の危険性とは
小児の肺炎は心臓障害、乳児や幼児の心不全、脳障害を引き起こす可能性があり、易怒性や眠気、脳浮腫などの...
成人の手足口病の原因は何ですか?
成人の手足口病の主な原因としては、免疫力の低下、病原体への曝露、生活環境の影響などが挙げられます。 ...
aldとは何か
ALD(副腎白質ジストロフィー)はまれな遺伝性疾患です。主に神経系と副腎に影響を及ぼし、神経線維を保...
生理的黄疸を治療するには?健康を改善するための黄疸の3つの合理的な方法
黄疸は乳児や幼児に非常によく見られる病気で、生理的黄疸と病的黄疸に分けられます。生理的黄疸は、一般的...
小児の下痢に対してどのような検査を行うべきか
生活の中で、小児下痢はよくある病気で、子供の健康を深刻に脅かします。子供が病気になると、親は特に不安...