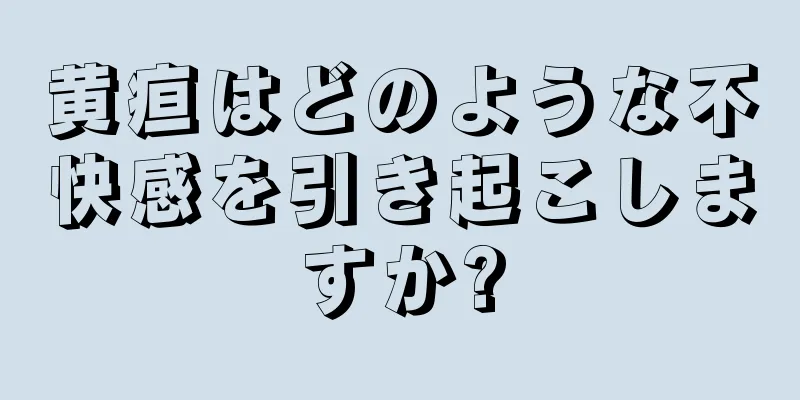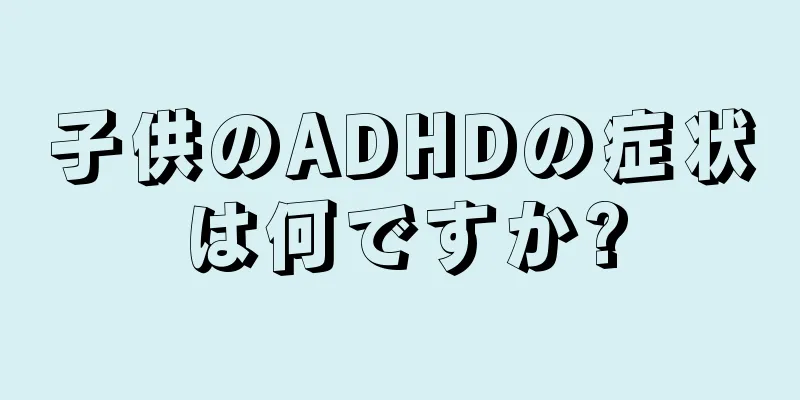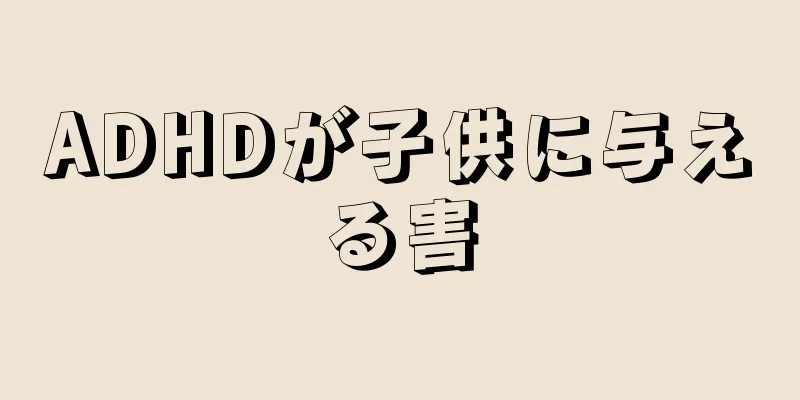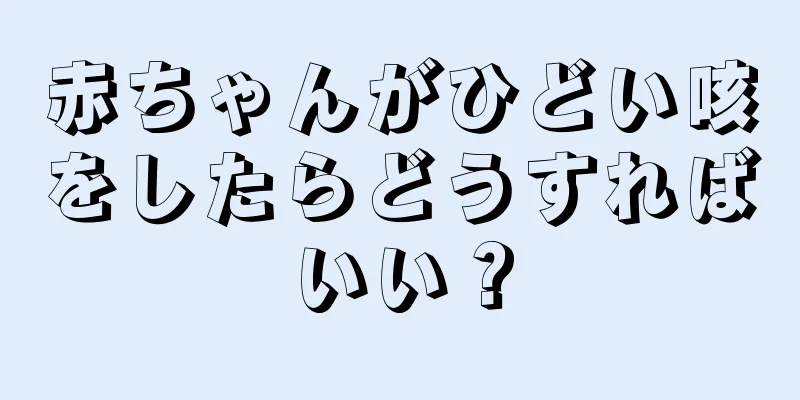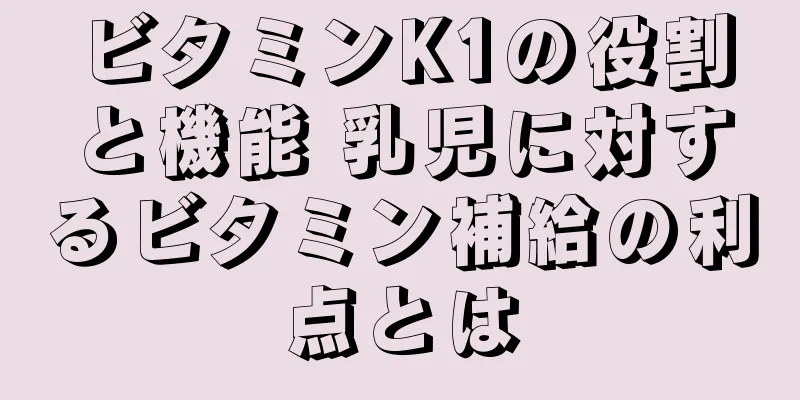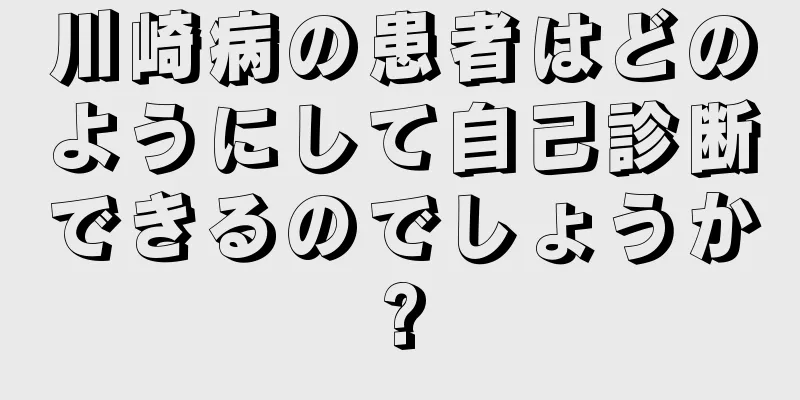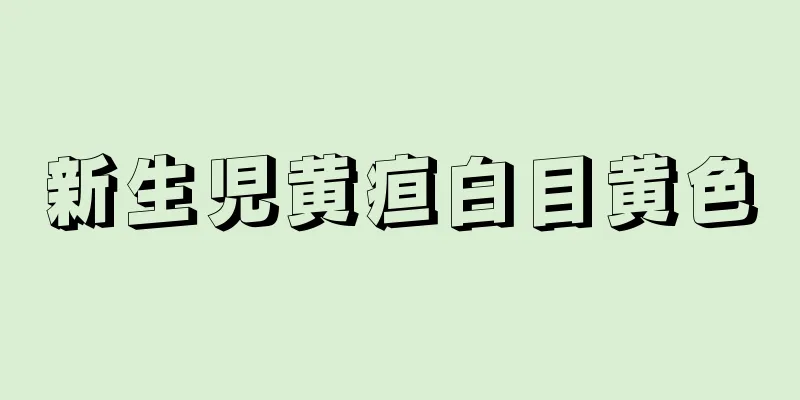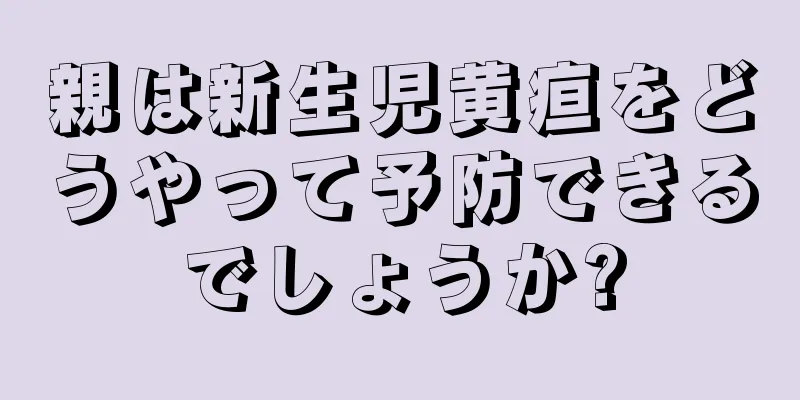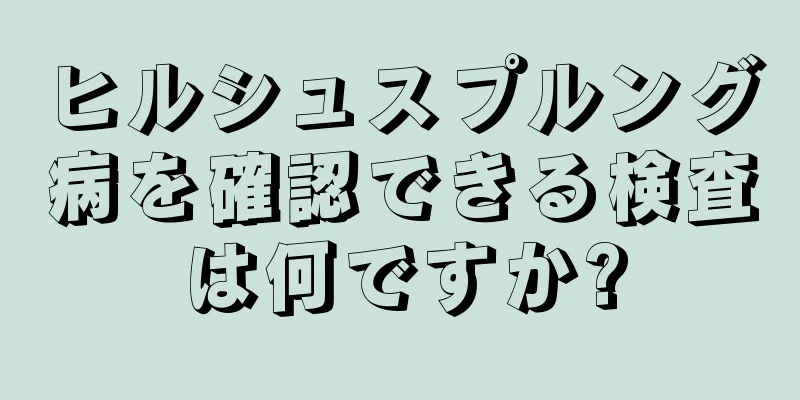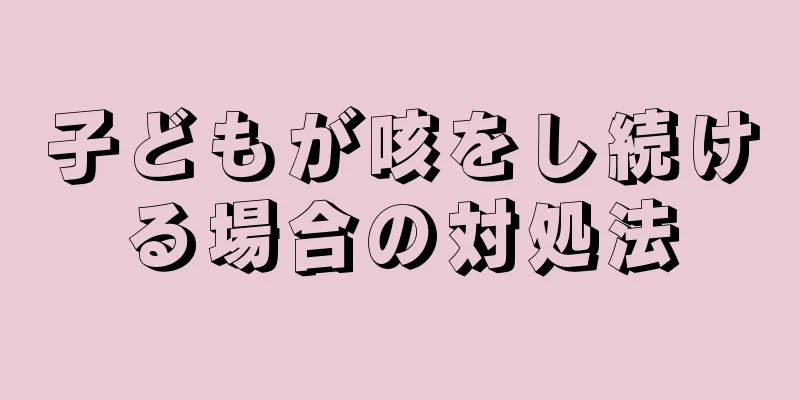新生児黄疸の原因
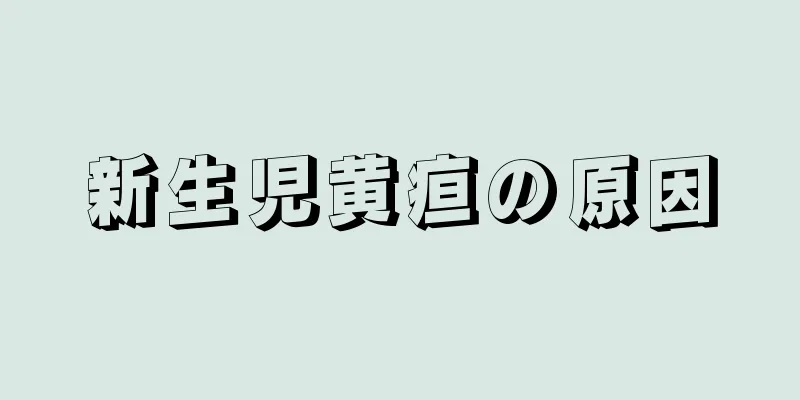
|
新生児黄疸は、ビリルビンの代謝異常により皮膚や白目が黄色くなる病気です。主な原因としては、ビリルビンの過剰産生、肝臓の処理能力不足、排泄障害などが挙げられます。治療法は黄疸の種類と重症度によって異なり、光線療法、薬物療法、交換輸血などが含まれる場合があります。 1. ビリルビンの過剰生成。新生児の赤血球の寿命は短く、破壊されると肝臓の処理能力を超える量のビリルビンが放出されます。 ABO または Rh 血液型の不適合など、母親と胎児の血液型の不適合により、溶血が悪化し、ビリルビンの生成が増加します。未熟児は赤血球が損傷を受けやすいため、黄疸のリスクが高くなります。溶血性黄疸に対しては、適時に光線療法または交換輸血療法を実施し、必要に応じて免疫グロブリンを使用して溶血を抑制する必要があります。 2. 肝臓の処理能力が不十分。新生児の肝機能は未発達で、ビリルビン抱合酵素の活性が低いため、ビリルビンを水溶性物質に効果的に変換して体外に排出することができません。授乳に関連する黄疸は、ビリルビン代謝を阻害する母乳中の特定の成分に関連している可能性があります。このような場合には、母乳育児を一時的に中止して粉ミルク育児に切り替えるか、母乳育児を継続しながらビリルビン値を監視することができます。 3. ビリルビン排泄障害。胆道閉鎖症や先天性胆管拡張症などの疾患は、ビリルビンの排泄を妨げ、閉塞性黄疸を引き起こす可能性があります。感染症や代謝性疾患もビリルビンの排泄に影響を及ぼす可能性があります。閉塞性黄疸の場合は、胆管再建や肝移植など、閉塞を解除する手術が必要となります。感染関連の黄疸には感染を制御するための抗生物質が必要であり、代謝性疾患には標的治療が必要です。 4. 生理的黄疸と病的黄疸の違い。生理的黄疸は通常、出生後 2 ~ 3 日で現れ、ビリルビン値が低下し、1 ~ 2 週間以内に自然に消えます。病的黄疸は早期に現れ、急速に進行し、長期間持続します。ビリルビン値が高く、核黄疸などの重篤な合併症を引き起こす可能性があります。親は黄疸の変化を注意深く観察し、異常が見つかった場合にはすぐに医師の診察を受ける必要があります。 5. 予防とケア対策妊娠中に定期的に検査を受けることで、母体と胎児の血液型の不適合などの問題を迅速に発見し、対処することができます。胎便の排泄を促進し、ビリルビンの再吸収を減らすために、出産後できるだけ早く授乳を開始してください。感染を防ぐために新生児の皮膚を清潔に保ってください。ビリルビン値を定期的に監視し、必要に応じて介入します。親は黄疸に関する関連知識を理解し、過度の不安を避け、潜在的なリスクを無視しないようにする必要があります。 新生児黄疸はよく見られる現象ですが、生理的原因と病理的原因を区別する必要があります。原因を理解し、タイムリーな介入と科学的なケアを行うことで、ほとんどの黄疸は効果的にコントロールでき、深刻な合併症を回避することができます。親は新生児の状態を注意深く観察し、医師と連絡を取り合って赤ちゃんの健やかな成長を確保する必要があります。 |
推薦する
生後2ヶ月の赤ちゃんは易壇井を飲んでも大丈夫ですか?
生後2か月の赤ちゃんが咳をしている場合は、効果が長く続く複合製剤であるイタンジンを飲むと、赤ちゃんを...
風邪や咳をしている子供に効く薬は何ですか?
子供の風邪や咳に効く薬は何ですか?風邪が原因で咳が出ている場合は、五茶や小青龍顆粒などの薬で治療でき...
新生児に発疹が出た場合の対処法 発疹が出ている新生児の日常的なケア方法
新生児の発疹は外用薬で治療することができ、一般的にはカラミンローションや福清軟膏を塗布し、抗ヒスタミ...
動脈管開存症は治りにくいのでしょうか?
動脈管開存症は治りにくいのでしょうか?動脈管は出生後10~15時間で機能的に閉鎖し始めます。生後2ヶ...
黄疸14.7は深刻ですか?
黄疸14.7umol/Lは血清総ビリルビンが14.7umol/Lであることを意味しますが、深刻な状態...
冬は小児肺炎の発生率が高い時期ですか?小児肺炎の4つの症状
冬は肺炎が最も多く発生する季節です。私の国では、小児の肺炎の発症率と死亡率は先進国よりも高くなってい...
トレハラーゼ欠乏症の対処法 トレハラーゼ欠乏症を予防する方法
ラクターゼは乳糖をガラクトースとグルコースに分解します。ラクターゼが不足しているため、患者は乳糖を摂...
日常生活で肺炎の子供をどのようにケアすればよいですか? 肺炎の子供をどのように治療すればよいですか?
小児肺炎は幼児期に比較的よく見られ、伝染性はありません。深刻な病気ではありませんが、母親は細心の注意...
子供の咳に対するマッサージテクニック
咳は子供によくある現象ですが、抵抗力が低下するため頻繁に薬を飲むことはできません。伝統的な中医学のマ...
子供の肺炎を予防する方法
新生児にとって、最大の脅威は環境の試練をいかに克服するかです。少しの風邪でも、風邪や発熱を引き起こす...
新生児黄疸の治療にはどれくらいの費用がかかりますか?
新生児黄疸の治療にはどれくらいの費用がかかりますか?ほとんどの赤ちゃんは新生児期に黄疸を発症します。...
母乳性下痢の治療原則は何ですか?
母乳性下痢の治療原則は何ですか?母乳で育てられた赤ちゃんは、粉ミルクで育てられた赤ちゃんよりも排便回...
新生児黄疸とは何ですか?黄疸は再発しますか?
医学的には、生後 28 日未満の新生児の黄疸は新生児黄疸と呼ばれます。新生児黄疸とは、新生児期のビリ...
インフルエンザを予防する方法は何ですか?インフルエンザにかかってしまったらどうすればいいですか?
1. インフルエンザの予防接種を受けるインフルエンザウイルスには多くの種類があります。世界保健機関...
子供の下痢の原因は何ですか?乳児や幼児の下痢を引き起こす要因は何ですか?
夏には、多くの子供が下痢になりがちです。夏の高温により、多くの細菌が繁殖します。赤ちゃんは抵抗力が弱...